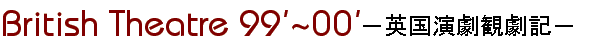

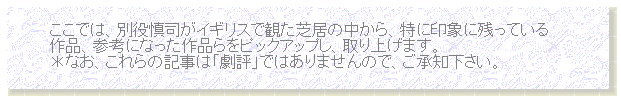








の「Hamlet」でフォーティンブラスを演じたRufus Sewellが、マクベス夫人には、Sally Dexter
があたる。この二人の演技は、確かに迫力があり、魅力的だった。
この作品で、いきなり、イギリスの俳優が誇るレベルの高さを如何なく思い知ることになる。日本の演技に常々辟易していた自分としては、どいつもこいつも演技のレベルが高いイギリスは衝撃であった。本当にイギリスの演劇の質は、俳優をはじめとする演劇人たちの技術の高さにある。
しかし悲しいかな、演技力は万能ではない。舞台は、最小限に舞台装置を省略し、俳優の演技力でこのマクベスの世界を表現しようとしていたが、どんなに演技の質が高くても、それは少々無謀な試みであったように思う。いくら、マクベスを熟知しているロンドンの観客といえど、想像力で補うには、もう少し装置や音響の助けを借りなくてはならない。
また、劇場のステージの高さは命取りになるということもわかった。というのも、床が見えないくらいに見上げる姿勢で芝居を観ると、そのぶん感情移入が弱くなるのだ。特に、このような俳優の演技力で観客に想像させてイリュージョンを作り出す場合、俳優を取り囲む空間も無視できなくなる。どうすれば、少ない装置でもイリュージョンを作り出すことが出来るのか、その答えはNT(National Theatre)でのOlivier Theatreで示されている。その話は、いずれまた。

日本では、宇都宮隆らが出演し、話題を呼んだ。
人種問題・同性愛・エイズなど、現代の若者が抱える問題を描いた、「This is America」といった作品だが、テーマの掘り下げ方も登場人物の描き方も非常に魅力的だった。「West Side Story」のような「大人が描いた若者」という感じではなく、「Rent」の中には作り物ではないリアルなものがある。
これだけ、真っ向から様々なテーマにぶつかり、これだけリアルに若者の生き方を描いたこの作品が支持を受けないわけがない。音楽も現代的で、まさに「現代版ミュージカル」。傑作古典が未だに顔となっているミュージカルにおいて、現代ミュージカルを創る上のヒントが隠されている。また、このアプローチの仕方は、ストレートプレイを行うぼくたちにとっても参考になる。
イギリスはアメリカと同様、様々な人種が混在する社会となっている。これは日本と全く異なる状況である。そんな社会にぼくは飛び込んでみて、改めて考え直すことが多かった。演劇をやる上で、芸術をやる上で、どうして日本人だけをみて表現していけるのか。この人種社会の中で「人間」「世界」というものがよく見えてきた。「Rent」は確かに「This is America」であり「アメリカ人」を描いているが、同時に「人間」「世界」というものも克明に描いている。ここにSTONEψWINGSが目指すキーが存在する。ぼくはたとえ日本人を描くときでも、常に「人間」を描くことを意識している。けれど、イギリスやアメリカのような国際社会でない日本では、それはとても難しいことである。

戯曲。オリヴィエ賞など幾つかの賞を手にし、日本を含む各国で上演された。プログラムによると39都
市明記されている。世界で現在、どのような新作戯曲が評価を受けているのか、確かめるためにも楽しみな公演だった。
内容は、四人の男女を取り巻く恋遍歴で、浮気本気の行ったり来たり。「愛してる」といっていても、次の場面では「やっぱり……が好き」と破局・乗り換え、またその繰り返し。右のボールがぶつかったら、左のボールが飛び出し、左のボールが戻ってきたら右のボールが飛び出すおもちゃと同じ。本当の愛などわからない。
というテーマはさておき、放送禁止用語の連発で、若い人を中心とした観客は腹を抱えて大笑い。天下の国立劇場でこんな芝居をやってしまうところがイギリスのすごいところだ。気持ちいいくらい遠慮会釈なくあけすけに描いたところに、受賞の理由があるようだ。脚本的には、無駄な部分もあるし、テーマはあれどもそんなに深くはぶつかっていない。名作戯曲と比べると、根本的に持っている質が違う。やはり、現代の劇作家のレベルはそれほど高くないようだ。傾向として、さっぱり風味の観客受けする作品が、よく新作戯曲の賞を受けているように思う。
しかし、今回のプロダクションは決していいとはいえない。演出も演技もお粗末で、これは準備不足が影響しているのだろう。というのも理由がある。この作品は、その前に上演していた「Remember
This」が早々と打ちきられ、その代演として入れられたものなのだ。「Remember This」は観にいったが、久しぶりに「退屈さ」を感じた芝居で、「NT、これでいいのか」と思ったけれども、やはりポシャった。(それでも、日本に持っていけば「映像効果を巧みに融合させた現代劇」などと評価され、少なからず衝撃を与えるだろう)
かつて称賛された「Closer」も、このリバイバルは上演プログラムの穴埋めにしかならない。いくら、演出家や俳優らがNTクラスの高い技術を持っていても、周到な準備と稽古をつまなければ、ろくな芝居にならないということがわかった。イギリス全体のレベルが高いだけに、欠点は非常に目立つ。

リー劇団RSC(ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー)のプロダクションとして、英国演劇界が誇る至宝
Sir Nigel Hawthorneを擁して、このニューミレニアムという記念すべき時期に上演する。これは大
変なことである。日英親交の文化交流ともなるため、プログラムにはトニー・ブレア首相も寄稿している。
取り上げ方も半端ではなく、上演前から巨大なポスターが地下鉄のあちこちに貼られ、期待の高さがうかがわれた。
蜷川は実はあまり評価していない。けれど、この蜷川版「リア王」は思っていたよりよかった。日本的
な要素は随所に見られた。松の絵を配した開閉式の巨大な扉、音楽、衣裳など、それらは単なるジャパネスクではなく、欧米スタイルと融和したセンスのあるものだった。また、上から砂を降らせ雨を現し、石を落とし落雷を現すなど、象徴的な演出も見られ感心した。照明の使い方もよかった。
Foolをつとめた真田広之の演技は、見た瞬間「日本の演技」だと思った。日本人の演技はイギリス人の演技とまるで違う。外面的な動きばかりが目立って、違和感がありリアリティーが伴わない。しかし、
明らかに異質な真田のFoolは、独創的といえば独創的。しかし、細かいリアとの心の交流はあまり見えなかった。
全体的にいえるが、俳優たちの演技を見て「蜷川は登場人物の感情、心理面など目に見えない部分
はほとんど指示を与えていないのだろうなぁ」と思った。Hawthorneにしても、他の役者にしても、感情の交流、心理の動きなどがほとんど伝わってこない。
とはいえ、個人的には結構満足のいくプロダクションだった。しかし、後日劇評を読んでみると、どこも散々ないいようである。こんなに悪い評価の劇評を読むのは初めてだった。真田の演技は宙返りしたくらいしか印象になく、日本的な演出も「松の絵が永遠を暗示しているなんてプログラム読まなきゃわからん」と一蹴、石を落とした象徴的な落雷の演出も「我らがHawthorneに当たったらどうしてくれるんだ」と
怒りさえ見える。そして、やはり登場人物の感情や心理が開拓されていないことが挙げられ「リア王を、シェイクスピアをわかっていない」という書きよう。辛辣である。これにはいささか蜷川に同情せざるを得ない。特に、象徴的な演出が理解されなかったのは口惜しいところだろう。


At the Old Vic Theatre on 4th February 2000 (Dublin Carol)
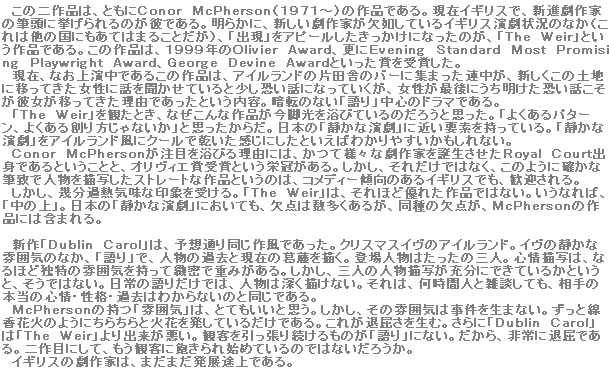

は、「The Other Place」という小規模のブラックボックスで行われた。日本によくある小劇場とほとん
ど違わない、このような狭い劇場でシラーの壮大なる「Don Carlos」をやってしまうのだからRSCはす
ごい。
俳優の持っている力は、すさまじいものがある。彼らの演技力で、ハムレットを更に激情的にしたような
「Don Carlos」を上演するのだから、観客は圧倒される。芝居が終わった瞬間、客の半数近くが一斉に立ち上がり、スタンディングオーベーションで役者たちを称賛した。これは驚くべきことだった。
本当にシンプルなステージである。舞台装置はほとんどないEmpty Space。わずか5mx5m程度のスペースで演じる。三方を取り囲む観客に、表情が見えるように見事な位置移動で。
王子ドン・カルロスの継母である王妃への恋愛、渦巻く陰謀、親友の死、スペインの王権を手にするまでの激しく荒々しい情熱的な役を主演のRupert Penry−Jonesは見事に演じきった。彼は、いつしか
「Hamlet」にも出演するだろう。そういうタイプであり、それだけの器を持っている。
とにかく、狭いブラックボックスで、観客を一瞬のうちにスタンディングオーベーションに導くのは、俳優の力が大きい。作品のテーマは重く、言葉も古くて難しい。しかし、圧倒的な俳優の演技力は、観客を感動に包み込む。
The Other Placeのような小劇場で、演劇活動をするものにとって、この「Don Carlos」は非常に勉強になるだろう。と、同時に最上の理想をも見る。このような芝居を創ってみたいと真剣に思い憧れる、
素晴らしい作品だった。

作品である。1956年この作品が現れるまで、上流社会向け喜劇が主流となっていた。それを、荒々しく
攻撃し、大人社会に埋もれた若者の生き様を描いたのが、John Osborneである。
この作品をNTが上演した。自分としては、演劇界にこれほど衝撃与えた作品というものがどんなものか
この目で確かめてみたかった。
舞台装置や演出は、おそらく当時の上演の雰囲気通りに作っていただろう。しかし、数十年前というの
は、戦後成長が生んだ製品(アイロン・ラジオなど)があるので感じるのだが、ドラマ自体はまったく古い
とは思わない。やはり人の生きていく苦しみや、どうにもできない苛立ち、怒りというものは、いつの時代
にもある。かつてこの作品の主人公Jimmy Porterは「怒れる若者」の代表とされたが、数十年経た今
でも、彼に共感できる。
この作品は、単に新しいことをやったからセンセーションを巻き起こしたわけではなく、共感できる普遍性が存在しているからこそ、大きな影響力となったのだ。ただ、それらが舞台の世界に現れていなかっただ
け。
感情を激しく外に出しているのがとてもいいと思った。そのエネルギーは確かに客席まで届く。本当の心情を隠し、上っ面だけを淡々と描いた作品など魅力は感じない。やはり人間の奥に響くものがなければい
けない。
そのように怒りや悲しみの感情をほとばしらせ、罵詈雑言を誰彼構わずぶっかけるJimmy役を、Micha
el Sheenが見事に演じていた。彼は声がいいだけでなく、その声にナイフを忍ばせることが出来る。そん
な感情表現の出来る役者だ。
この作品の一番の欠点は、Jimmyの妻、Alisonを取り戻すべく登場する父親であろう。精神的に疲れ
果てたAlisonの元にやってくるが、そのときの登場のみ。役者の演技も、それまでの芝居の流れからする
と明らかに異質で、よくない。

内容が自閉症を扱った重いテーマであり、俳優の演技もすさまじい。これらが生きるのは狭い空間である。Whitehall Theatreのようにプロセニアムで、観客と舞台に距離と段差が生じた劇場では、観客は客観的に見てしまって、この種の重いテーマから本能的に逃げてしまう。しかも、ロンドンの観客は重いテーマの暗い作品は好まない。これが非常に残念な傾向だ。芝居は娯楽と考える人が圧倒的に多い。
劇作家であるぼくとしては、現代的テーマに挑んだこの作品に非常に好感を持てた。「自閉症」とその裏に
隠された「性的虐待」。ぼく自身も「花と君」という作品の裏に、父親による「性的虐待」を暗に含めた。こういった、現代の抱える問題の、その裏に迫ったアプローチは評価すべきだと思う。演劇は我々の世界を映す鏡なのだから。
しかし、圧倒されたのは俳優の演技だ。これには恐れ入った。メインキャラクターとなる、自閉症のLynnとセラピストのAnna。この二人の、感情が爆発されたときの演技……美しい女優が涙だけでなく、鼻水まで垂らすほど激しく、観るものを圧倒するすさまじさだった。こんな演技を、ガラガラの劇場で、毎回のようにやっているのだ。その俳優魂に深く感銘を受けた。これこそ俳優だと思った。
ロンドンの観客も、このような現代劇の新作を受け入れてほしいものだ。それがイギリス演劇の一番足りないところだろう。
「Anna Weiss」は非常にインパクトの強い、素晴らしい作品だった。もちろん精一杯の拍手を送った。